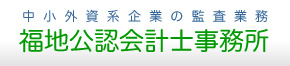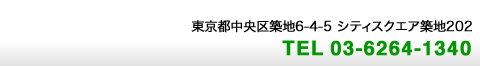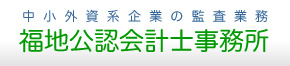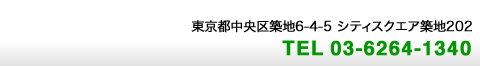|
すでに移行手続に向けて準備を開始されている法人様も多くいらっしゃるかと存じますが、いよいよ移行期限の平成25年11月末日まであと2年余りとなってまいりました。
これから準備を開始されようという法人様も、まだ十分間に合います。移行手続には当所のサポートをご利用下さい。以下、お目通し頂けましたら幸いです。
|
| 当事務所のご利用をお勧めしたい理由は、以下の通りです。 |
- 公益認定手続及び一般認可手続は、新制度のためどの法人様も手探り状態だというのが本当のところです。当事務所は公益法人会計業務を10年以上も行ってきており、その道のエキスパートです。
- 日本を代表する公益法人会計のエキスパート「公益認定.JP」と業務提携しており、新制度でのノウハウを蓄積しています。最新の情報による多角的なサポートをお約束します。
- 各法人様の資金状況に見合ったサポートのご提案をいたします。
新制度移行に関する手続は、法人様が想像されている以上に手続は煩雑でかつ申請の仕方を間違えると、事後的に解散せざるを得なくなる等のリスクが発生します。したがいまして表面だけ取り繕った粗雑なコンサルタント等に業務を依頼されてしまいますと、事後に大変なリスクを背負うことになります。
- 当事務所では、移行手続のポイントを的確にアドバイスします。
- 公益法人会計に関するエキスパートが直接担当いたします(公益法人アカウンタント・日本公認会計士協会公益法人会計委員会委員長)。
- 移行後の申請書類作成なども完全バックアップします。
- 現状の顧問税理士さんを変更せずに、サポート可能です。
|
| 公益移行認定のための具体的ポイントは? |
|
公益認定法に規定されている、公益認定基準を満たすことが必要ですが、その中で特に以下が重要なポイントとなります。
- 貴法人の何が公益目的事業要件に該当するか
まずスタートはここからです。公益認定法において列挙されている公益目的事業はあいまいな記述が多く含まれているため、うちの事業は公益事業に該当するのだろうか?が具体的に不明確な点があります。過去の経緯や税法上の扱いのみを基準として、公益性を考慮するのは不十分です。公益目的事業と認定されるための不特定かつ多数の者への利益増進に寄与すること、を如何に説明できるか、は重要なポイントとなります。
- 公益目的事業比率は50%以上を保てるか
いわゆる、「公益目的事業比率要件」と言われるハードルです。公益事業比率が50%を超えない、といった問題を抱えていらっしゃる法人様は多いようです。これについては、①の公益目的事業の範囲を如何に広げられるか、がポイントとなります。これらにつきましては、個々の法人様の事業内容を吟味することと他の事例を参考にしてクリアできる場合があると考えます。
- 収支相償をきちんと満たせるか?
公益目的事業と認定されるために、その収入は公益目的事業にかかる費用を上回ってはならない、とされるハードルが収支相償です。たとえば、公益目的事業収入がどうしても費用を上回ってしまうという場合、その収入を公益事業収入から外す・収入の使途を他の事業目的に指定してしまう・特定費用準備資金を設定する、などの方法により収入を切り落とすことが可能かもしれません。見落としている点が解決につながる可能性があります。
以上はポイントの一例ですが、今回の公益法人制度改革による申請はすべての法人様にとって初めてのケースとなりますし、申請事例も正直なところまだ多くはありません。法人様の事業内容等も千差万別で、一様の解決方法など無いというのが現実です。だからこそ私どもでは、今までの経験を生かしながら個々の法人様特有の事情を勘案しながらFace to Faceでコンサルティングさせていただきます。まじめにじっくりとお話を聞かせていただきたい、それが当方の最大の売りです。
ぜひ、公益法人移行申請に関するご相談を私どもまでお待ち申し上げます。
|
| 代表コンサルタント |
 福 地 徳 恭 福 地 徳 恭
昭和37年生まれ
福地公認会計士事務所 代表
公益法人アカウンタント
公認会計士・税理士
お客様のためにFace to Faceで全力でサポートします。
|
| 顧問監修コンサルタント |

小 渋 高 清
昭和37年生まれ
公益認定ドットJP 代表
小渋公認会計士事務所 代表
日本公認会計士協会東京会・公益法人委員会委員長
公認会計士・税理士
日本を代表する公益法人会計のエキスパート
|